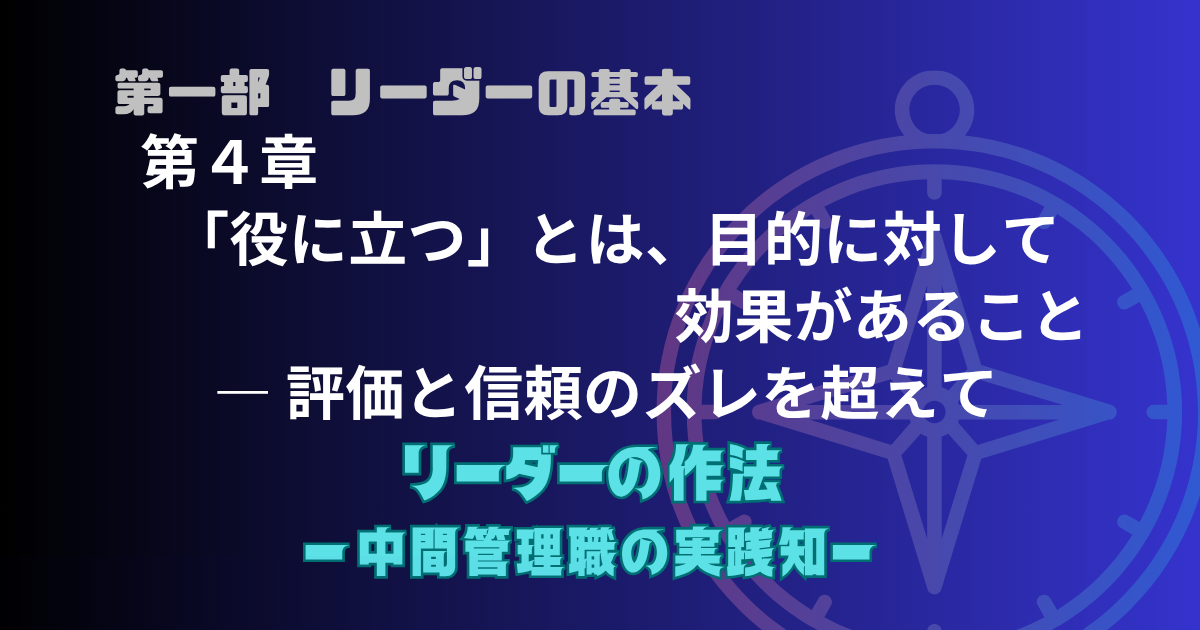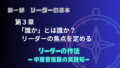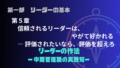評価への自然な欲求
中間管理職として働いていると、上司からの評価が気にならないわけがない。
「褒められたい」「出世したい」──それは人間としてごく自然な感情だ。
むしろ、そうした思いがあるからこそ頑張れるという側面もある。
褒められたい気持ちの落とし穴
しかし、この「褒められたい」という気持ちに引っ張られすぎると、判断基準が他人の期待に傾いてしまう。
たとえば、上司に嫌われないように無難な報告や発言ばかりを繰り返し、部下に対しては必要な指摘や改善を避けてしまう。あるいは、周囲の期待を気にするあまりプレッシャーに押しつぶされてしまう。
結果として、リーダーとしての本質的な役割を見失い、チームの成長を阻害してしまう。
立ち返るべき視点
ここで立ち返るべき視点がある。
私たちは、組織の目的達成のためにリーダーとして任じられているという事実だ。
「役に立つ」の本質
つまり、「役に立つ」とは、組織やチームの目的に対して実質的に効果のある行動を取れているかで判断されるべきであり、「誰に気に入られるか」ではない。
現実のズレと判断の軸
とはいえ、現実には上司の意向と現場の現実がずれることも多い。
部下の希望と、成果に向けた最適な方法が一致しないこともある。
そんなとき、リーダーは「この判断は、目的にどうつながるか?」を軸に、自らの行動を選ばなければならない。
時には、厳しい判断を下し、周囲の反発や摩擦を覚悟して行動することも必要だ。
信頼と真の評価
だが、そのように「評価されようとせず」に、「本当に役に立つ」行動を積み重ねていった人こそが、最終的に信頼され、真の評価を得る。周囲の反発を受け入れる覚悟、と書いたが最終的には「君がそこまで言うのなら賭けてみよう」と感じてもらえる存在になっていくということだ。
評価を求めて右往左往するのではなく、目的に立脚して判断し、行動し、結果で語る。
それこそが、最も遠回りに見えて、最も確かな「評価への道」なのだ。
読者への問いかけ
自分の判断が「組織の目的の達成に役立っているか」を考えたことがありましたか?
次章予告
次章も、ほめられようとしなくても信頼を勝ち取ることで応援してもらえるという話をしたい。