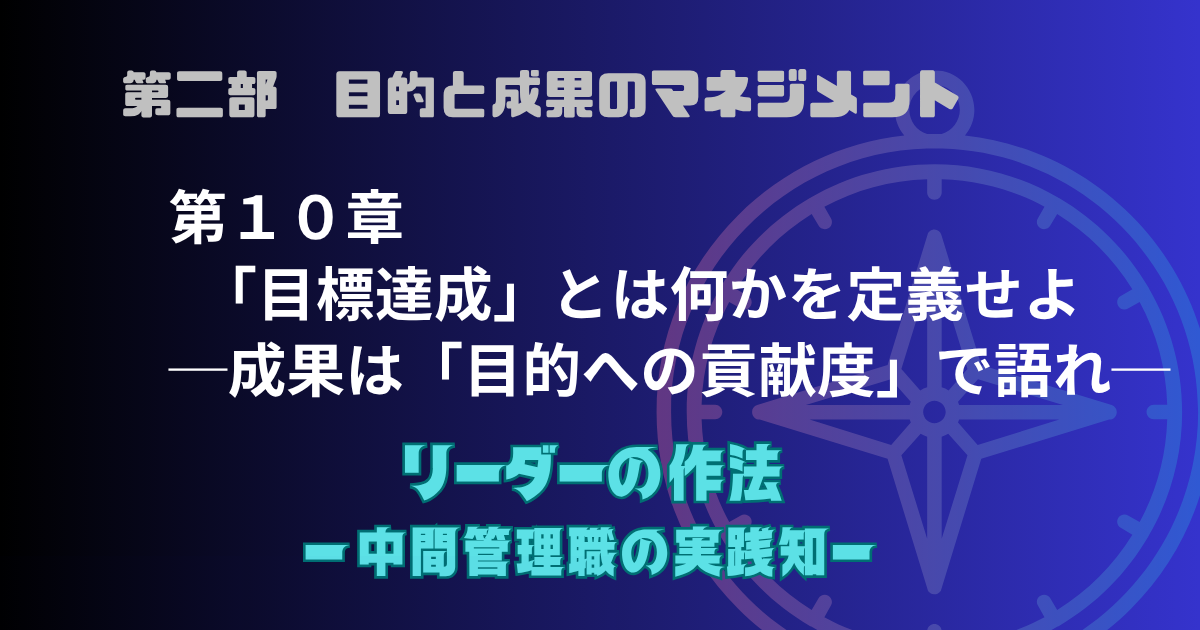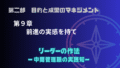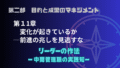曖昧な目標に潜む落とし穴に潜む落とし穴
目標面談で、部下が「関係部署と連携します」「情報共有を進めます」と語るのを聞くたび、私は内心で首をかしげてしまう。
それ自体は悪くない。だが「連携した結果、何が変わるのか?」と尋ねると、多くの場合、答えに詰まる。
まるで「動いていること」自体が目標になってしまっているのだ。
「努力=成果」という誤解
これは、けっして部下が怠けているわけではない。
特に数値目標を立てにくい業務では、「何をもって成果とするか」が曖昧になりやすい。
そのまま進めば、最終的には「努力したからOK」という“やってる感”にすり替わってしまう。
しかし本来、成果とは努力の量ではなく、目的への貢献度で測られるべきものだ。
成果を定義する問いかけ
前章でも書いた通り、成果の定義はチームメンバーと共有しておく必要がある。だから私は、メンバーとの目標設定の場でこう問いかける。
「この取り組みが成功したら、誰がどんな状態になっている?」
変化を言語化することの重要性
たとえば「情報共有を進める」なら、それによって「意思決定が早くなる」「ミスが減る」「説明の精度が上がる」など、何らかの変化が起きるはずだ。
この変化を言語化できなければ、前進しているかどうかを確かめることもできない。
数字でなくても測れる状態目標
数字で測れなくてもいい。
「どんな状態になればいいのか」「どんな反応が返ってくればいいのか」「どんな判断が可能になればいいのか」──
こうした状態目標に落とし込めば、進捗確認も評価も建設的になる。
曖昧さがもたらす停滞
逆に曖昧なままだと、「まあ一応やってますけど…」という空気に飲まれ、チームの動きは鈍る。
目標とは、動くための理由であり、進んでいる実感を得るための起点だ。
リーダーの言語化力が鍵
それを本当に機能させるには、「達成したら何が変わるか」を明らかにすること。
リーダーの言語化力が、チームの前進を左右するのである。
読者への問いかけ
- 「この目標が達成されたら何が変わるか」を言語化しているか。
- 「努力量」ではなく「目的への貢献度」で成果を評価しているか。
- 数値で測れない仕事も「理想的な状態像」で定義しているか。
- 成果定義を部下と共有し、確認のたびに立ち返っているか。
- 「動いていること」と「成果を出していること」を混同していないか。
次章予告
次章から、チームの事業を進めるにあたってリーダーに求められる「変化」を感じ取る力について考えたいと思います。